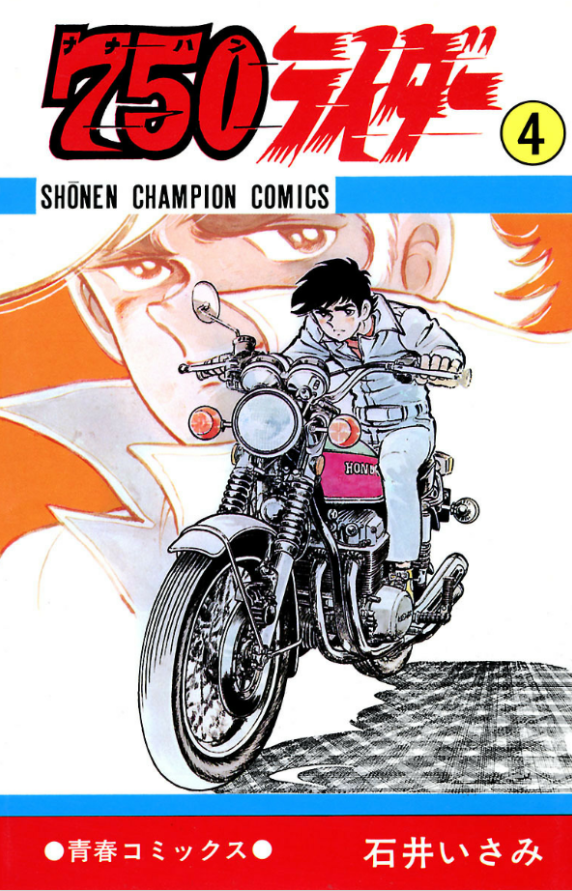〈昭和の忘れもの〉バイク編㉓
【ホンダ CB750four】ショートストーリーVersion


かつて文学少女だったマドンナに振られて以降、「新たな出発(たびだち)」などと浮かれていた気概が怪しくなった。
気付けばタンデムシートは空席のままだし、昔のように玄関先までバイクで乗り付けて「走りに行こうぜ」と誘える仲間もいない。新たな同好の士であるK(750RS)やDさん(GL400)は多忙を極め、気まぐれに付き合わせるのは気が引けた。もとより遊び上手で多趣味な彼らは、バイクにどっぷりというわけではなかった。端からこちらとは温度差があったのだ。だが、逆に彼らの趣味に腰が引ける自分もいたのだからお互い様だ。
隣の駅まで愛車のCB750fourで出掛けたある日、事件は起きた。日頃の主人のストレスが伝播したのか、用事を済ませてさて帰ろうといつもの手順を踏んだのに、CBが目を覚まさないことでパニックになった。キーボックスに挿したキーを捻り、セルボタンを押したが反応がない。ハンドル中央のインジケーターを見ると、ニュートラルを示すグリーンのランプが点いていなかった。ギアを確かめたが、ポジションに間違いはない。改めてキーを捻り、念のためクラッチレバーを握ってセルボタンを押した。やはり無反応だ。試しにキックペダルを引き出して踏み抜いたが、結果は同じだった。
素人判断で電気系統の問題だろうと踏んだ。原付の「ダックス」あたりならともかく、パラレルフォーのエンジンはもちろん、視認できない電気系統のトラブルではお手上げだ。プロに任せるしかない。動揺を堪えながら、とにかくバイク店に連絡することにした。
近くの公衆電話から電話をかけて窮状を伝えたが、返事は冷ややかなものだった。
「今日は手がないから引き取りは無理だな。明日の夕方なら何とか」
失望と憤りを覚えたが、相手も切実な現状を答えたに過ぎない。怒りをぶつけたところでどうしようもないが、このまま路上や近隣の空き地に愛車を放置することは論外だった。あれこれ考えを巡らせたが、最終的な答えはシンプルだった。エンジンはかからないが、駆動部のどこかが破損したというわけではない。ホイル(タイヤ)がロックしているわけではないから押すことはできる。ならば、何としても自宅まで自力で運ぼうと決めた。
電車で1駅、直線距離で2㎞強である。歩きなら30分。頭でそう計算したが、すぐに現実は単純ではないことに気付いた。地図上なら確かにそんなものだが、実際は2点間の中程にけっこうな高低差の坂がある。所によって勾配は12%を越え、しかも総重量240㎏近い不安定な2輪の車体を、支えながら押していかねばならないのだ。
考えただけでぞっとしたが、覚悟を決めてハンドルを掴み、両足に力を込めて踏ん張った。初めの1メートルは苦労したが、動き出すと安定した。なんとか押していけそうだ。
無心に押していると次第に冷静になれた。
(待てよ。何とか坂道を避ける手はないのか?)
幸い地元ということで道路状況はしっかり頭に入っていたので、シミュレーションしてみる。谷の部分を避けて高台の縁を大回りして行けば、最小限の高低差で乗り切れるかもしれない。当初考えた最短ルートをあっさり捨て、できるだけ緩い勾配の道路を選んで繋いでいく。まるで迷路ゲームのようだ。
幾通りかを頭の中で試し、ようやく可能性の高いルートが浮かんだ。ただし、距離は2倍近くになってしまう。果たしてどのくらいかかるのだろう。2時間、いや3時間くらいはかかりそうだ。それでも、勾配10%強の坂道をナナハンを押して上る事と比べれば遙かに現実的だ。
自慢じゃないが腕力に自信はない。体格的にも、本来ならナナハンライダー不適合と言われても仕方がないほどの細身である。それでもバイクを扱うコツは心得ているつもりだったし、実際、取り回しで倒したことはなかった。
そんな自負を糧に、必死にCB750fourを押し続けた。フラットな路面では辛うじて老人の散歩程度の速さだが、僅かでも上り勾配になると這うような速度になった。速度が落ちても、坂を下ろうとする重力が加わるので押す力は反比例的に増加する。しかも、車体が直立状態なら最小限の力で支えることができるが、僅かでも向こう側に傾いたら引き戻すことはできない。したがって手前に重心が来るように車体を傾け、車重を腰で支えながら、かつハンドルを直進に保たなければならない。静止状態でもきついこの体勢のまま、バイクを押し続けなければならないのだ。
誰かを罵りたい気分になったが、何の役にも立ちはしない。余計な思考を排除し、バイクを支えながら歩を進めることに集中した。途中でガソリンスタンドの看板を見かけたが、2輪にとって給油以外に何の助けにもならないことを経験済みなので素通りした。
「ガス欠ですか?」
通りかかったライダーが声を掛けてきたが、スタンドを無視した状況を察してばつが悪そうに走り去った。その後ろ姿を見送り、緩やかな起伏をいくつか乗り切った時点で1時間が過ぎていた。春先の穏やかな日だったが、すでに上半身は汗まみれで、両手の握力は殆ど失われていた。危機的な状況だ。
ところが、最大の難関はこの先に待ち構えていた。どう工夫しても、一箇所はきつい坂道を通過しなければならなかった。それがこの先に待っている。皮肉にも緩やかに一旦下り、そして少しずつ上っている。最大斜度は5度くらいだろう。歩く分には気にもならないレベルだが、バイクを押していくとなると話は別だ。アスリートの強化トレーニングのメニューにあってもおかしくないレベルだ。しかも、距離は優に300メートルはある。しかし、ここまで来てしまった以上後戻りはできない。死に物狂いで挑むしかなかった。
先ずは微かな下り坂を、足がもつれない程度の速度に保ちながら慎重に進んだ。ここで転倒してしまったら元も子もない。そしていよいよ上り坂だ。深呼吸をし、攻撃態勢を整える。いざ、戦闘開始だ。
一歩踏み出す毎にずっしりとした重量感が腕から肩、背中から下半身へと反撃してくる。歯を食いしばり、全身の力を掻き集めて押し返す。僅かにタイヤが動き始める。この機を逃さず、全体重をかけながら足で路面を蹴る。ようやくタイヤが回転し始め、数メートル進む。しかし、足の筋肉はすぐに音を上げ、回転速度はあっという間に落ちて、止まってしまう。後退しないようにフロントブレーキをかけ、呼吸を整える。この間も力を抜くことはできない。
タイミングを計り、再び同じ事を繰り返す。正に地獄の坂道ダッシュの無限版だ。ただし、ダッシュと言いながら大きな負荷がかけられているので、気持ちとは裏腹にその速度はスローモーションの如くである。
坂道はおよそ300メートル。5、6メート毎に、意に反したストップアンドゴーを繰り返して進むしかない。坂の途中で力尽きれば、バイクもろとも道路に叩きつけられるだけだ。そうなったらただでは済まない。ここは市街地へ向かう公道だ。路側帯が設けてあるが、車道は多くのクルマが行き交っている。誤って車道側にバイクを倒したら大事故になりかねない。
他人にそんな緊張感が理解されるはずもなく、信号でクルマの流れが一時的に止まると一斉に好奇の目に晒され、時折声も掛けられる。
「ガス欠?」「故障?」「パンク?」「大丈夫?」
本心から心配してくれる人もいるが、
『ざまぁ見ろ』『ナナハンを乗り回していい気になってるからだ』
そんな嘲りの視線も少なからず浴びせられた。殆どは被害妄想の類いだろうが、絶望的な状況の中では、ポジティブな思考は浮かばなかった。
殊に原付バイクのライダーに冷笑されたときは心が折れかけた。自分にはそんなつもりはなくても、相手から見れば日常的に大型バイクに“煽られて”いるような感情を抱いていたのだろう。残念だが如何ともし難い。原付の最高速度は30㎞と決められている。50㎞規制の公道では追い抜いていくしかないのだ。
肉体的、精神的苦痛を味わいながら、拷問のような1時間半が過ぎ、ようやく坂道の頂に辿り着いた。やっとの思いでサイドスタンドを出し、車体が安定したのを確認すると、崩れるように道路に座り込んだ。全身から汗が噴き出し、腕の痙攣は治まらない。両足も自分のものではないかのように重く、二本の肉の丸太が付いているように思えた。
通行人が怪訝そうな視線を投げていく。もうどうでも良かった。このままここで寝転んでしまいたかった。しかし、まだ終着点ではないのだ。起伏は少ないとはいえ、まだ1㎞近い道程が残っている。
ボロボロになった身体に鞭打ち、何とか立ち上がった。ハンドルを掴み、サイドスタンドを蹴り上げる。シートを腰に預け、苦行を再開する。
この先の道路はほぼ平坦なはずだが、体力的には限界で、頭の芯は朦朧としていた。不思議なことにバイクの重量が感じられない。決して軽くなったわけではなく、感覚が麻痺してしまったのだ。それでも無意識にバランスだけは保っていた。自分とバイクが“ハ”の字、いやどこかの熱血先生が説いた“人”の字に支え合い、ノロノロと進んでいく。
もう周囲の好奇の目は気にならなかった。自分の行為が何なのかも定かではなくなった。ナナハンの重量を全身で支えながらひたすら前進する。左右の脚で一歩一歩踏ん張りながら、機械的に身体とバイクを進めていく。トランス状態とでも言うのだろうか、思考は完全に遮断され、視野もスポットライトのように限定的になった。
それでも身体が覚えていたのだろう。いくつかの信号を過ぎ、横断歩道を渡り、路地を右に折れ、左に折れ・・・我が家に近づくにつれて、靄が晴れるように視界が広がっていく。
そしてついに、ようやく、我が家の鉄錆の浮いた門扉が見えた。「ゴール!」心の中で叫びながら、道路と家の敷地の境界線を“二人”で通過した。庭の一角の定位置にCBを停め、サイドスタンドに車重を預けた瞬間、総べての緊張が解けて尻餅をつくようにへたり込んだ。息苦しくて酸素を求めて喘ぐのだが、肺には僅かな空気しか送り込まれない。必死に深い呼吸を繰り返す。両腕はもう1センチも上がらない。腰から下はまるで砂袋のようで、動かすどころか感覚さえ失われていた。
その場に仰向けに寝転んだ。我が家の庭だ、誰に遠慮する必要があるだろう。忘れていた土の匂いがした。青い空を背景にして薄い雲が流れていた。僅かに首を動かすと、そこにはいつもと変わらない愛車の姿があった。一瞬、「故障」とか「修理」といった単語が過ぎったが、刹那に掻き消した。
僅かだが身体の感覚が戻ったので、地面を這っていき、家の外壁に背中を預けるよう凭れかかった。視界いっぱいにCB750fourの車体が収まり、午後の遅い時間の太陽が、銀色のタンクを優しく照らしていた。
今はただ、“相棒”と共にゴールできた達成感の余韻に浸っていたいと思った。